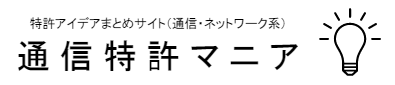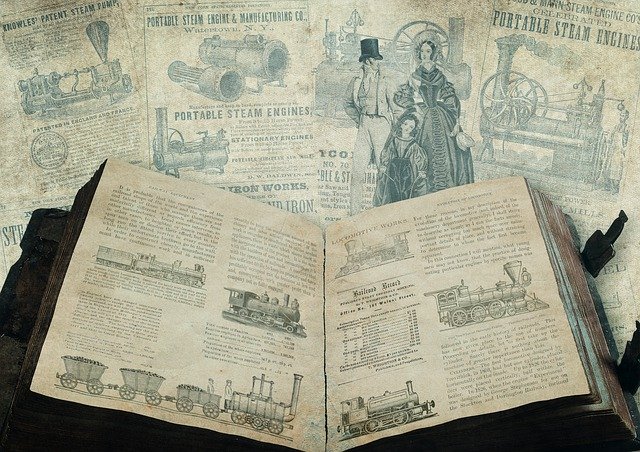特許ってむずかしそう。特許とったらすごそう。よく知らんけど。
そんなふうに思っているひとも多いと思います。
ニュース記事などでは、ちゃんと認められた特許なのか、まだ認められていないものなのか、はっきりしない表現があって、よく知らない人は誤解してしまいそうです。注意が必要です。
この記事では、「認められた特許」なのか、「まだ認められていない」のか、この違いに着目して、ニュース記事の表現を分析します。
私は特許事務所で仕事をしていて、しかも特許の文献を読んで勉強をするスタイルをずっと続けてきています。ニュース記事の表現が紛らわしいなっていうのに気づくことも多いです。
以下で説明していきます。
特許出願(特許申請)をしただけでは、まだ特許として認められていない
企業の特許についての動きがあると、次はこんな製品が出るか?、とか、次のバージョンアップでこんな機能が追加されるか?、というような内容のニュース記事が出ることがあります。
でも記事をよく読むと、特許の取得ではなくて、特許の出願(特許の申請)(*1)をしただけの段階であることもあります。
特許の出願(特許の申請)(*1)をしただけでは、特許の最初の手続をしただけであり、特許が認められたわけではありません。特許として認められているか、まだ認められていないかは、大きな違いがあります。
まず、このあたりの違いについてシェアします。
*1:ちなみに、特許について「申請」という言葉がよく使われますが、法律上は「出願」という言葉が使われます。
特許をとるには:特許出願(特許申請)のあとに審査を受けることが必要
特許法では、特許の出願のあとに、審査官が審査をして、特許として認められるときに特許権が成立する、という流れになっています。
特許の出願をしただけの段階では、まだ審査がされていません。特許の出願をしただけの段階は、書類の形式が整っていることが確認されたという段階です。
言い換えると、発明のアイデアについて何も確認されていないという段階です。
これに対して、特許権が成立した段階では、審査がされて、特許として認められたものだけが残っている状態です。言い換えると、発明のアイデアについて審査官が審査をして、特許として認めるという判断をしたという段階です。
このように、特許の出願をしただけの段階と、特許の取得をしたこととは、大きな違いがあります。
なので、特許の出願をしただけの段階と、特許の取得をしたこととは、大きな違いがあります(*2)。
*2:詳しく知りたい方はこの本をどうぞ。
特許の審査の前なのか、後なのかが大事、でもまぎらわしい
ニュース記事などではなるべく注目を集めたいせいか、読み手が「特許を取得した」と受け取ってしまいそうな表現が多く使われていると思います。誤解を招きそうな表現が多いのが現実だと思います。
「特許を取得した」という話の流れにして、次世代の製品がこうなるかも、っていう話につなげることができるからかもしれません。記事を書いているひとは、特許が認められた段階なのか、まだなのかをちゃんと知っている、はずですが。
以降では、ニュース記事などでよく見る表現が、どんな意味なのか、特許をとったことを意味しているのか、そのあたりを説明していきます。
特許について注意が必要な表現の例
注意が必要な表現の例について、以下で具体的に説明していきます。
「○○社が特許の出願をした」
「○○社が特許の出願をした」というのは、特許の出願をしただけの段階を意味しています。そのままです。
多くの場合、このような発表は、特許の出願をしたすぐ後になされることが多いです。逆にいうと、出願から1年もたってからこのような発表をすることは少ないです(しても間違いではないですが)。
まだ審査はなされていないので、特許をとれるかどうかわかりません。特許の出願をした直後では、その内容も公表されないので、内容もわかりません。
正直なところ、どんなアイデアであっても特許出願はできてしまうので、この段階では、あまり騒ぎ立てることはありません。
これに似た表現として、「特許を出した」、「特許を申請した」などもあり、同様の意味です。
「●●社の特許が公開された」
「●●社の特許が公開された」というのは、2つの場合があり、これだけでは判断できません。
具体的には、「特許出願が公開された」場合と、「特許が公開された」場合の2つの場合があります。
前者「特許出願が公開された」の場合には、審査前の状態の書類が公開されます。
審査前の状態の書類が公開されるときは、タイトルが「公開特許公報」になっています。また、最初のページの右上に「特開●●●●-●●●●」という形式の番号がついています。「特許」ではありません。
このような公報は、まだ特許が認められているわけではないです。「特許の出願をした」というのとだいたい同じ感じです。
後者「特許が公開された」の場合には、審査に通った状態つまり特許権の内容を示している書類が公開されます。
審査に通った状態つまり特許権の内容を示している書類が公開されるときは、タイトルが「特許公報」になっています。また、最初のページの右上に「特許第●●●●●●号」という形式の番号がついています。
これが、特許の内容を記載している公報です。審査官によって特許が認められたものです。
これに似た表現として、「●●社の特許の内容が明らかになった」もあり、同様の意味です。
「○○社が特許を取得へ」
これはまぎらわしい!「特許を取得」したかのように思えてしまいます。
でも、特許を取得したのであれば、「特許を取得。」になるはずで、「へ」はつかないはずです。なので、この表現は、「特許を取得」したのではないと考えられます。
では何を意味しているかというと、よくわからないです。
推測ですが、特許の成立より前で、ニュース記事になりそうことといえば、特許出願くらいだと思うので、特許の出願をしたことを意味していると思います。
実際にこの表現が使われていた記事は、「特許の出願をした」ということを意味していました。
特許を取得したと読み取れる表現は何か
上記の例では、「特許を取得した」と安心して受け取れる表現がありませんでした。
ではどのような表現があれば、「特許を取得した」と受け取れるのでしょうか。
例えば、「特許を受けた。」、「特許を取得した。」、「特許が成立した。」と言い切る表現があれば安心できます。「特許」が「特許権」になっていてもほぼ同意です。
あと、「特許を開放した」、「特許のライセンス契約をした」、という表現は特許をとったことを前提としているので、特許がすでに取得できていると判断することができます。
今日のみどころ
今日は、特許に関するニュース記事などで注意しなければいけない表現についてシェアしました。
間違えないように注意しましょう。間違った情報を広めてしまうことのないようにも注意しましょう。
特許の手続について知りたい方にはこの本をおすすめします。