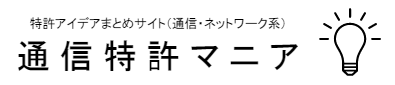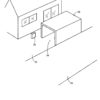主婦の知恵のようなアイデアを特許ネタにするのが、主婦にとって有利だと思います。
この記事を読めば、主婦の知恵のアイデアを特許ネタにもっていく思考の流れがわかります。
私は特許事務所で実務を8年経験しており、大企業、社員数人の企業や、個人の発明の特許化のお手伝いをしています。主婦の立場なら、主婦の知恵のアイデアを特許ネタにするのがもっとも有利。有利なところで戦って特許をとれた事例もたくさん知っています。
この記事を読みながら自分のアイデアを検討して、問題-課題-解決の3ステップで整理すれば、特許ネタを生み出すことができます。
以下で詳細に説明します。
主婦の知恵のアイデアを特許ネタにして利益を生む
主婦が特許をとって一攫千金。という話題がたまにあります。一攫千金までいかなくても、主婦の知恵のようなアイデアで商品化されて利益を生んでいるケースがあります。
特許は、技術的なアイデアで一定の要件を満たせばとることができます。
では、主婦はどんな分野で特許や商品化を狙うのがよいでしょうか。
まったく知らない分野でいきなりアイデアを出すのは無理でしょうから、使ったことがあるもの、知っているものの分野で特許を検討することになると思います。
例えば、スマホや携帯電話、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、照明器具のような電子機器や家電製品、インターネット上の販売システム、オークション、SNSなどの仕組みも特許になりえます。
これらの分野では実際に大量に特許がとられていますが、メーカが戦略的にやっています。そのため、主婦のアイデアで特許をねらっても、利益につなげるのはなかなか難しい。
日常生活に密着した道具がよいかも
そういう分野より、日常生活に密着した道具などの物のほうが、主婦に有利です。有利なところで戦うのが勝つ秘訣。利益につなげやすいです。
例えば、家事、育児、介護などのなかで使う道具や情報の工夫は、特許になりえます。
いままでにまったく新しい物をつくった、という場合、もちろん発明になります。いまある商品の改良、例えば、一部に何かくっつける、穴をあける、という工夫でも発明になりえます。
主婦の知恵の特許ネタの検討から出願まで
主婦の知恵のアイデアを特許ネタにするには、どんなことを考えないといけないか。
そのアイデアの最終的な形や機能を考える必要があります。
それに加えて、なぜぞのような形にしたのか、なぜそのような機能が必要なのかが伝わるように、その特許によって解決される問題や課題も整理しておく必要があります。
そこで、商品化の前のアイデア出しから特許ネタを決めるまでしないといけないことをまとめると以下のとおり。これらが1つのストーリーになるようにします。
2.課題を見つける
3.課題を解決できる解決策を見つける
順番に説明していきます。
1.身近な問題をみつける
上記のとおり、主婦の知恵のアイデアを特許ネタにしていくには、日常生活に密着した物のアイデアを検討するのが近道だと思います。
家事、育児、介護などで道具を使って何かするときに、うまくいかないところや、不便なところを見つける。それが、特許のストーリーの出発点となる「問題」になります。
また、もっとこうだったらいいのに、という方向で考えるのも有効です。その裏返しが、現状の「問題」ということになります。
身近な問題の例
身近な問題の例を挙げます。例えば、以下のような感じのものです。ご参考に。
- ○○を固定したいのに動いてしまう。
- 2つの○○が混ざってしまう。
- 素手で○○できない。素手で○○すると手が荒れる。
- 片手で○○できない。片足で○○できない。
- ひとりで○○と○○を同時にできない。
- ○○にスペースをとりすぎる。
- ○○するのに時間がかかる。
- ○○するのに●●が必要である。
- ○○がすぐになくなる。
- ○○がうまくできない。
- 細かく○○できない。
- ○○を●●と間違えてしまう。
- いつも○○するのがめんどう。
シンプルに1行くらいにまとめます。「○○」や「●●」というところに実際の物や行動の名前を入れます。あくまで例ですので参考程度にしてください。
そのほか、このサイトにある特許公報の紹介記事に、それぞれの特許の問題の説明をしていますので、参考にしてください。
物の使い方で問題を回避してしまうことがないように気を付ける
問題を見つけるときに気を付けたいのは、その問題を、その道具の使い方を工夫して回避してしまわないようにすること。
上手な主婦ほど、無意識のうちに、その物の使い方を工夫して問題を回避してしまうことがあります。
例えば、「○○を固定したいのに動いてしまう。」という問題に気付いたものの、「動かないようにするには、隣に●●を置いておけばいい」と工夫してしまう。このようにすると、問題を回避してしまい、問題ではなくなってしまいます。
このように上手に問題を回避するのは、日常生活では大事なことなのですが、特許ネタを考えるときには、ちょっとがまんしておきましょう。
2.課題を見つける
問題を見つけたら、次に課題を設定します。これは問題を裏返しにすればOK。
上記の問題の例を裏返しにして課題を設定すると、こんな感じになります。これもあくまで例ですので参考程度に。
- ○○を動かないように固定する
- 2つの○○がまざらないようにする。
- 素手で○○することを回避する。
- 片手で○○できるようにする。片足で○○できるようにする。
- ひとりで○○と○○を同時にできない。
- ○○に必要なスペースを削減する。
- ○○する時間を削減する。
- ●●なしで○○できるようにする。
- ○○の長持ちさせる。
- ○○をうまくできるようにする。
- 細かく○○できるようにする。
- ○○を●●と間違えるのを回避する。
- ○○せずに●●できるようにする。
3.課題を解決できる解決策を検討する
そして、課題を設定したら、その解決策を検討します。ここが主婦の知恵であり、特許ネタになる部分であり、一番大事な部分です。
「○○を固定したいのに動いてしまう。」という問題に対して、「○○を動かないように固定する」という課題を設定したとしたら、どのようにそれを実現するかを考えます。例えばこんな感じ。
- 突起をつけて、突起が隣の物に引っかかるようにする。
- 穴をあけて、隣の物の突起が穴に入るようにする。
- シートを挟んで滑りにくくする。
- 凹凸をつけてすべりにくくする。
ここまでできたら、いちおう特許ネタになります。
あとは特許要件を満たすことが必要
これで特許ネタがいちおうできました。次の問題は、この特許ネタで特許をとることができるかどうか、ということ。
少なくとも、すでにお店で売っている商品や、ウェブサイトを検索してみて出てくるようなアイデアでは特許はとれません。
特許をとることができるかどうかは、上記の解決策の部分が、いままでにないものであるという要件と、いままでのものから容易に思いつくものでないという要件などを満たす必要があるからです(*2)。
そのような要件を満たせるように、上記の解決策の部分にもうひと工夫を加えたりする検討をしておきましょう。
例えば、解決策として取り付ける部分の形を工夫してみたり、もともと別の機能のためにあるものを兼用するようにしてみる、とか、いろいろ検討しましょう。
*2:これらの要件をそれぞれ、「新規性」、「進歩性」といいます。これらが代表的な特許要件ですが、そのほかにもあります。詳しくは特許事務所と相談しましょう。
出願するまでは、解決策を人に言うのもはNG
ここで大事な注意点があります。特許をとるアイデアは、上記の通り新規性が必要です。
自分でひとに話してしまった、ブログで紹介してしまった、商品化して売ってしまった、ということがあると新規性を失ってしまい、特許をとることができなくなります。
詳しくはこちらを読んでください。
1→2→3の順番でなくてもてOK。いったりきたりして考える
上記では、1、2、3という番号を付けて説明しました。思考の流れとしてもこれが自然なのでこのように説明しました。
でも実際に検討しているときは、1→2→3という順番でなくてもOKです。
解決策を最初に思いついたのなら、その解決策によって解決される課題は何かを考えるとよいです。そしてその課題を裏返して問題を作る。
実際に特許事務所でクライアントのお話を聞いていても、解決策が一番最初にあって、それに合わせて課題と問題を作るということがよくあります。これでまったく問題ないんです。
いったりきたりしながら、1→2→3のストーリを作ればいいです。
特許出願しましょう
特許のストーリーができたら、特許事務所に出願の相談をするか、自分で出願の手続をはじめましょう。こちらの記事を参考にしてください。
これで特許をとるための特許出願の手続が完了します(*3)。
*3:特許に手続きについて知りたい方はこちらの本をざっと読んでください。
今日のみどころ
主婦の知恵のアイデアを特許ネタにして出願するときの手順を説明しました。
特許で利益を出すには難しさもありますが、一歩を踏み出さなければ利益を得ることはできません。一歩踏み出してみましょう!うまくいけば一攫千金!