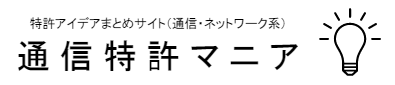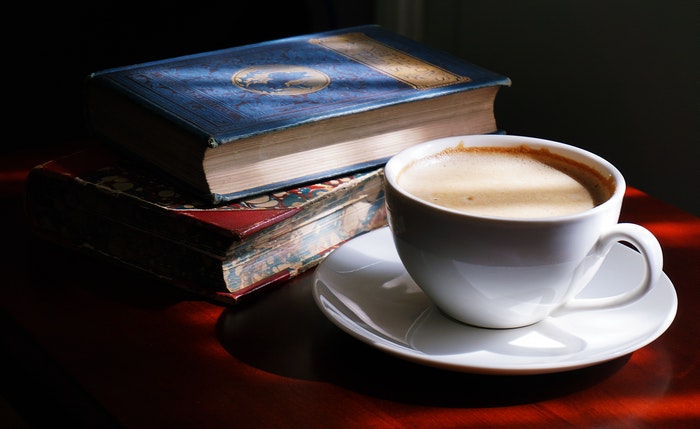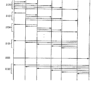日本人であれば日本語を使うことができる、普通はそう思うのですが、ちゃんとした日本語で文章を書くことはけっこう難しいです。
論文や特許明細書などの技術文書は、間違いがないように論理的に記述されていないといけません。ちゃんとした日本語を書くことができないと、意味がわからない技術文書になってしまう、というか、技術文書になりません。
ちゃんとした日本語を書くために知っておかないといけないことがまとめられている本を紹介します。少し読んでおけば、気を付けながらちゃんとした日本語を書けるようになります。
私は過去に企業の研究開発職として論文を書いたり学会発表したりした経験があり、いまは特許事務所で特許明細書などの技術文書を作成する仕事をしています。
文章を書くときには、ここで紹介する本を読んだことを頭の片隅に置いています。一度読んで頭に入れておくのがおすすめの本です。どれも超ロングセラーの本で、はずれなしです。
日本語の「は」と「が」の使い方を説明した良著『象は鼻が長い―日本文法入門 』
『象は鼻が長い』というだけの短い文。完全に意味を理解することができますが、どうして「象は」のところが「は」で、「鼻が」のところが「が」なのか。『象の鼻が長い』、『象の鼻は長い』という文とどう違うのか、と、考えたことはないでしょうか。
助詞の「は」と「が」について、日本人であればよく考えずにうまく使っているのですが、その違いに焦点をあてて、「てにをは」の使い方を詳しく説明している本です。
「は」は文章の主題を表していて、また、「は」は「がのにを」を代行するというのです。「は」と「が」をいっしょくたにして主語を示すものと教えられることがありますが、ちょっと違う面もありますよね。あと、「は」と「が」とで、係り先が違ったりもします。このあたりのことについて例文を示しながらわかりやすく説明されています。
この本を読めば、技術文書を書くときに「は」を使うのが良いのか、「がのにを」で表現できることなのか、気を付けながら文章を書くことができるようになります。読み手にとって読みやすい日本語になります。
あと、仕事上で日英の翻訳者とよく話をしますが、「は」と「が」の違いは、翻訳者も結構なやんでいることがあります。日英の翻訳者にとっては、翻訳元の日本語の書き手がどうして「は」や「が」を使ったのか、知ることができるかもしれません。
読み手にわかりやすい文章を書きたいときに読んでおきたい『【新版】日本語の作文技術』
日本語のわかりやすい文章を作文するための「技術」を説明している本です。
わかりやすい文章を書く才能がある人もいますが、そのような才能がなくても日本語のわかりやすい文章を作文する技術を習得することは、だれにも学習可能だと説明されています。
具体的には、修飾語の係りの関係をわかりやすくするやり方、句読点の使い方、助詞の使い方などの説明があります。
特に、文章を書く時に、修飾語の係りがわかりやすくなるように気を付けているか、そうでないかで、わかりやすさがだいぶ変わります。
また、助詞の使い方の説明では、上で紹介した『象は鼻が長い』を例にしてさらに著者が補足をして説明をしています。さらに理解が深まります。
技術系の文章の基本ルールを知りたいときに『知的な科学・技術文章の書き方―実験リポート作成から学術論文構築まで』
この本は、私が大学生のときに勧められた本です。
技術系の論文や実験リポート(実験レポート)の書き方は、あまり丁寧に教えてもらえないと聞くことが多いです。私もそうでした。
この本には、技術系の論文や実験レポートを書くときの文章の基本ルール、製図やグラフなどの書き方が例を挙げてわかりやすくまとめられています。卒業論文の書き方もあります。
具体的には、実験レポートの構成として、実験目的、実験方法、実験結果、考察の書く項目で書かないといけないことがまとめられています。
技術論文の構成の場合、中心部分は上記と同じような感じですが、その前に書く緒論や、その後に書く解析や結論部分の説明もあります。
技術系の論文や実験レポートを書くのにあまり慣れていない人は、まずこの本の内容を知っていくつか書いて感覚をつかむのがオススメです。そのあとに、自分なりの書き方、自分の研究に適した書き方にあうようにアレンジしていきましょう。
今日のみどころ
技術文書を書く人におすすめの基本書を紹介しました。
まずはこれらの本の内容をおさえて、そのあとに自分のアレンジを加えていくのが、技術文書を書けるようになるための近道だと思います。