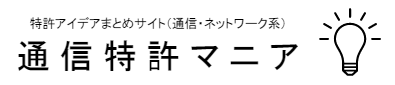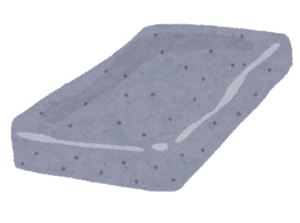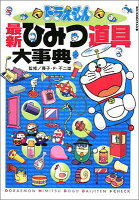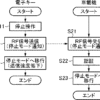新しい製品のアイデアを検討するとき、消費者(ユーザ)の要求を反映する「ニーズ志向」で考えると、市場に受け入れられやすいといわれています。
でも新製品を開発する側のエンジニアはシーズ志向になってしまいがちです。
私はいまは特許事務所でクライアントの発明の特許化のお手伝いをする仕事をしていますが、前職は企業で研究開発をするエンジニアを10年経験しました。私もシーズ志向で考えていましたが、どうやったらニーズ志向で考えることができるのかということもよく考えていました。
その経験をふまえてニーズ志向で考えるおすすめのやり方をシェアします。シーズ志向で考え始めたことでも、そのニーズのあわせて考えると市場に受け入れられやすくなります。
以下で実例を挙げて説明します。
ニーズ志向とシーズ志向の意味、違い
新しい製品のアイデアを検討するときの方向性として、「ニーズ志向」と「シーズ志向」があります。
「ニーズ志向」と「シーズ志向」の意味や説明はいろいろなところでなされているので、ここでは簡単な説明だけ記載します。
ニーズ志向というのは、消費者(ユーザ)の求める製品や機能を作っていくという考え方です。消費者が欲しいものを作っていくという方向で考えます。
シーズ志向というのは、企業がもっている技術を生かして、新しい技術や製品を作っていくという考え方です。企業が提供できるものを作っていくという方向で考えます。
どちらも良い面と良くない面があるといわれていますが、ユーザの要求を反映するニーズ志向のほうが、市場に受け入れられやすいといわれています。
技術者はシーズ志向で考えがち
技術者は、これまでの技術の延長で、もっと良い技術を開発しようと考えがちです。これはシーズ志向の考え方です。
例えば、いまの通信技術より、通信速度を上げる、通信量を多くする、データの欠落を少なくする、という方向性で新技術を検討する。
これがユーザが考える方向とあっていれば問題ないのですが、あまり求めていないものだと、技術だけが突っ走ってしまうことになります。
これまで通信速度を上げたりしてビジネスがうまく進んできたので、今後も通信速度を上げればうまくいくだろうという考えがあると思います。こうすると、別の新しいことを考えるより、いままでの延長で進めるほうが、失敗が少なく安心できるという気持ちもあるかもしれません。
技術者はこのように考えてしまいがちです。明確な課題をもてるし、ある程度実現できそうなアイデアを持っていることも多いので、ほかのことを考えるより安全です。
でも、こんな感じで研究開発を進めてしまうとあまりよくないこともあります。消費者がおいてけぼりになってしまうことがあるんです。
シーズ志向で考えたことも、ニーズをちゃんと考える
消費者が製品やサービスを購入するのは、消費者が求める技術や製品が提供されているときです。
消費者が求める技術を見つけて、それを提供していくのがニーズ志向。消費者が求めるものとあっていれば、消費者はそれを購入します。
なので、仮にエンジニアがシーズ志向的に技術開発をするとしても、それがユーザの要求にあっているということを示していくのがよいです。
例えば、携帯電話の通信規格が3G、4Gとどんどん進化して、次は5Gだといっています。こういうのは、通信速度を上げる、遅延を減らすというだけのシーズ志向という見方もあります。
でも、5Gになるとユーザが、いまよりさらに高精細な映像を自由に見られるようになる、とか、自動車の自動運転に使えるというニーズも併せて説明していくと、ニーズ志向のように見えてきます。
ニーズ志向にもっていく方法/ドラえもんのひみつ道具を利用して発想
ではどうやってニーズ志向で考えるかということをシェアします。自分で考えたり、未来を想像したりするだけでは、限界があるからです。
そこで利用できるのが、映画やまんがなどで登場する技術や製品です。その代表例は、みんなに人気のドラえもん。
ドラえもんに登場するひみつ道具は、ユーザの問題を解決する直感的な形をしています。一方、技術的な実現性はあまり考えられていない。ニーズ志向で必要な考え方でできているわけです。
ドラえもんに出てくるひみつ道具から製品のアイデアを得て、いまの技術で近いものが実現できるかと考えるのが1つのやり方です。
以降で例を挙げて説明します。
「どこでもドア」に近いものは何か
ドラえもんのひみつ道具の「どこでもドア」。ドアをくぐるだけで一瞬で行きたいところに行ける道具です。もし実現すれば、物流や人の流れが完全に変わってしまうことになります。
では、いまの技術で「どこでもドア」そのものを実現することはできるかと考えます。当面は無理だと思います。
次に、いまある技術で「どこでもドア」に近いものは何か、と考えます。
頭をやわらかくして少し考えてみてください。
「どこでもドア」に近いものは、新幹線
いまある技術で「どこでもドア」に近いもの。私なりの答えは、新幹線です。飛行機も当てはまります。
新幹線は、駅の場所が決まっているので「どこでもドア」のようにどこへでも行けるというものではないです。また、「ドア」の形でもないです。
でも、「人が短時間で遠くに行く」というニーズをある程度達成しているといえると思うんです。
昔の人は江戸と大阪との間を移動するのに片道2週間くらいかかったそうです。これだと往復するのに1か月かかってしまいます。
それが今では、新幹線を使って東京-大阪間が3時間です。日帰りできます。
昔の人にしてみれば、大阪と江戸の間を6時間で往復できるなんて信じられないですよね。そういう意味で「どこでもドア」に近づいているといえます。
将来、リニアモーターカーができれば、東京大阪間が1時間になるといわれていますし、その後100年、200年とたてば、東京大阪間が10分くらいになるかもしれません。さらに「どこでもドア」に近づくわけです。
「ほんやくこんにゃく」に近いものは何か
次の問題。ドラえもんのひみつ道具の「ほんやくこんにゃく」。このこんにゃくを食べると、自分が話す言葉が相手の言語に翻訳され、相手が話す言葉が自分の言語に翻訳されます
いまの技術で「ほんやくこんにゃく」を実現できるかというと、これも難しいでしょう。こんにゃくを食べると言語が変わるというのは難しい。
では、「ほんやくこんにゃく」に近いものは何でしょうか。
その1つの答えは、ポケトーク(POCKETALK)のような翻訳機です。
自分が発した日本語の音声が一瞬で外国語の音声に変換される。反対に、相手の外国語の音声が一瞬で日本語の音声に変換される。
勉強など面倒なことをしなくても、外国の人とコミュニケーションをしたいというニーズを満たしているといえます。
今日のみどころ
このような形でニーズ志向的な考え方のトレーニングをしましょう。
特に最近では技術がどんどん進んで、新しい発想とお金さえあればモノが作れるという感じもあります。新しい発想でモノを作り出していきましょう!
ちなみに、ポケトーク(POCKETALK)は、単なる話のネタではなく、けっこう話題になっている実際の商品です。SIMありモデル、SIMなしモデルなど、いろいろバリエーションがあります。ほしい方は、アマゾン、楽天などでさがしてください。
ドラえもんの秘密道具をざっと調べるならこちら。『この一冊で、きみもひみつ道具博士に!! 中にはたっぷり、ひみつ道具が約1600こ。』ですよ。
職場の本棚にこんな本があったらいい職場だなって思えるかも。あたまをやわらかくしていい発明をしましょう!